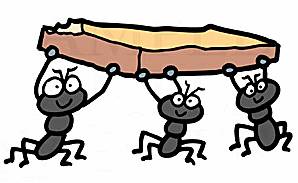【ありとキリギリス】
(ありとキリギリス)
イソップ物語の中に、「ありとキリギリス」というのがあります。さて、日本ではどんなストーリーでしょうか?
■夏の間、ありたちは冬の間の食糧を貯めるためにせっせと毎日毎日働いています。それに引き替えキリギリスは、毎日毎日歌を歌って遊び呆けて働こうとはしません。
 「ありさん 。どうして君たちはこんなに暑い夏の日に、そんなに汗水垂らして働いているんだい?」…キリギリスは、ありさんを小馬鹿にしたような感じで言いました。
「ありさん 。どうして君たちはこんなに暑い夏の日に、そんなに汗水垂らして働いているんだい?」…キリギリスは、ありさんを小馬鹿にしたような感じで言いました。
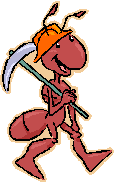 「何を言うんだキリギリスくん! 今のうちに働いておかないとすぐに寒い冬がくるんだよ。君も歌を歌うのは程々にして、少しは食べものでも運んだ方がいいんじゃない!」…ありはキリギリスに忠告しました。
「何を言うんだキリギリスくん! 今のうちに働いておかないとすぐに寒い冬がくるんだよ。君も歌を歌うのは程々にして、少しは食べものでも運んだ方がいいんじゃない!」…ありはキリギリスに忠告しました。
 「馬鹿だなぁ〜。せっかくの夏だよ! 好きなことをして楽しまないとつまらないじゃないか!」…キリギリスは、再度ありさんを小馬鹿にしたような感じで言いました。
「馬鹿だなぁ〜。せっかくの夏だよ! 好きなことをして楽しまないとつまらないじゃないか!」…キリギリスは、再度ありさんを小馬鹿にしたような感じで言いました。
■やがて秋になり冬が来ました。冷たい雪が降る冬の夜、ぼろぼろになったキリギリスがお腹をすかして彷徨っています。そして、キリギリスは偶然明かりがついた1軒の家を見つけます。
窓から中を覗くと、あの時のありさんたちが沢山のご馳走を前にして、楽しそうにパーティーを開いているではありませんか。
 「ありさん! 僕はお腹ぺこぺこなんだ〜。食べ物を少し分けてもらえませんか?」…キリギリスは、ありさんに頼みました。
「ありさん! 僕はお腹ぺこぺこなんだ〜。食べ物を少し分けてもらえませんか?」…キリギリスは、ありさんに頼みました。
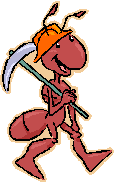 「おやぁ〜、あの時のキリギリスくんじゃないか! 夏には毎日歌って遊んでいたのだから、冬には雪の中で歌って踊って遊んでいればいいんじゃない?」…ありはキリギリスにそう言って、キリギリスの願いを冷たく断わりました。
「おやぁ〜、あの時のキリギリスくんじゃないか! 夏には毎日歌って遊んでいたのだから、冬には雪の中で歌って踊って遊んでいればいいんじゃない?」…ありはキリギリスにそう言って、キリギリスの願いを冷たく断わりました。
★このように”あり”に言われたキリギリスは、「夏の日に遊んでばかりいたこと」を深く反省し、大きな泪を流しました。…終わり
■日本においての「ありとキリギリス」のストーリーは、儒教的な思想の影響かもしれませんが、「努力する物は報われる、怠ける者には罰がある。」というような教訓になっています。
しかし、各国に伝わる「アリとキリギリス」の結末は1つじゃないそうです。
(A)ありはキリギリスをかわいそうに思って、家にいれて食べ物を恵んでやった。キリギリスはありに感謝して、夏の間遊び暮らした自分を反省した。
(B)ありは「夏のように歌っていたら」と言って食べ物を与えずにべもなく追い払った。キリギリスは飢えと寒さで死んでしまった。アリは餓死したキリギリスを食べた。
(C)キリギリスは、ありの家にいれてもらい、音楽を聞かせる代わりに沢山の食べ物をチケット代としてもらった。この後コンサートが大好評で、ありの行列で毎日大にぎわいとなり、音楽家として幸せに暮らした。
皆さんは、どの結末がお好みですか?
さて、最近では「ありとキリギリス」の解釈(ストーリー・人物像)が変わってきています。
人類の歴史は、農業時代→工業時代→IT時代と変化しています。私が思うに、数千年続いた「農業の時代」では、人の力が生産性を支える重要な要素でありました。そのため、「働かざる者、食うべからず」が通用し、このような「ありとキリギリス」のストーリーがピッタリと合う時代だったと思います。しかし時代は、「工業の時代」になり、そして「ITの時代」へと大きく変貌しています。もはや、社会を動かす力は、人力よりも、情報力や知識力が重要な要素となっています。情報力や知識力が社会を制すると言っても過言ではありません。
IT社会での「ありとキリギリス」の解釈・考え方は、特に若い世代で次のようなイメージに傾きつつあると言われています。
(キリギリスのイメージ・人物像 )

■自分の特技を一つ持ちオンリーワンを目指す人
■特技を生かし金持ちになれる人
■常に夢・向上心を持つ人
■ベンチャー精神を忘れない人
(ありのイメージ・人物像)
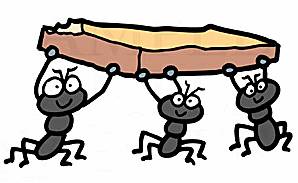
■個性が無くみんなと同じでなきゃダメな人
■こつこつと働くばかりで趣味がない人(過労死するかも?)
■融通が利かない人
■ベルトコンベアの前で流れ作業をこなすだけの人
■自分の能力を磨かない人・発見出来ない人
ソフトバンクの孫さん、楽天の三木谷さん等、IT関連企業で多くの人が社会で大活躍されています。(マイクロソフトのビル・ゲイツさんが世界の代表かな?) このようにITの時代では、「護送船団主義、親方日の丸、寄らば大樹の陰」から外れた生き方をしても、頭角を現すチャンスが有るのです。これからの時代は、オンリーワンを目指すキリギリスの生き方が注目されるのかもしれませんね。